薬を実際に使えるか
医師国家試験では、
とか、
などと、疾患-薬剤の対応関係についてはよく学習していてそれなりに覚えると思います。
しかし、
- 内服薬であれば1日何回、1回何錠飲む?
- 注射製剤であれば濃度は?投与速度は?
といった、自分がその状況に遭遇した時に実際に治療できるか?といった点において、必要な知識は全くといって身に付きません。
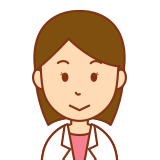
「この薬って実際どうやって使うのかしら?」
臨床に出たころの初期研修医が、必ずと言っていいほどつまづくとこなのかなと思います。
で、まあ、最初のうちはすでに患者さんが飲んでる薬だったり、上級医に「あれ出しといて」と言わた薬だったりを、逐一添付文書で確認して必死になって用法・容量を覚えるだけでなく、あまたある薬剤の一般名と商品名を対応させて頭に叩き込むということを誰もがやっているんじゃないかなと思います。

「こんなことしてて覚えられるようになるの?」

「もっと楽に、簡単に薬剤名とか使い方を覚える方法はないの?」
この途方もない作業をやっている時、特に初期研修医に成りたての2,3カ月は、毎日のように思うことでしょう。私は思っていました。
しかし、これに答えるとするならば、
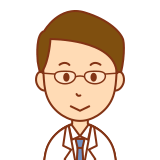
「楽な、簡単な方法はありません。」
となります。
繰り返し繰り返し添付文章を確認して、日々の診療でその薬剤を実際に使っていれば、だんだん覚えられるようになっていきます。
色々な薬剤に日常的に触れて、コツコツと勉強する以外に、近道はないと思います。
これでこの記事を終わってしまっては、あまりにも芸がないというか、読んでくれる方が何も得しないので、せめて、その地道な学習の助けになれるように、よく使う薬剤(成人)の使用例一覧表を作ることにしました。
あくまで筆者が「よく使う!」と思うもののみ、独断と偏見で一覧にしておりますので、参考程度にご覧いただければ幸いです。
また、以下をテンプレにして、副作用や禁忌等を自分なりにカスタマイズしてメモ帳に保存しておく、という使い方もぜひしていただければと思います。
解熱・鎮痛薬
アセトアミノフェン製剤
体温調整中枢、中枢神経に働く
- 錠剤、1錠200, 500mg
- 細粒、1g中200mg
- 解熱/鎮痛で用法用量が異なる
解熱の場合
- 1回300~500mg
- 1日2回内服
- 1日最大1500mgまで
鎮痛の場合
- 1回600~1000mg
- 投与間隔4~6時間
- 1日最大4000mgまで
- 坐剤、1剤100, 200mg
- 1回1~2剤
- 投与間隔4~6時間
- 注射製剤、1袋100ml(アセトアミノフェンとして1000mg)
- 1/2~1袋を15分で投与
- 解熱/鎮痛で用法用量が異なる
解熱の場合
- 1回300~500mg
- 1日2回、投与間隔4~6時間
- 1日最大1500mgまで
鎮痛の場合
- 1回600~1000mg
- 投与間隔4~6時間
- 1日最大4000mgまで
NSAIDs
COX1,2阻害によるプロスタグランジン生合成阻害
- 錠剤、1錠60mg
- 1回1錠、1日3回内服
- 頓用1回60-120mg
- 錠剤、1錠100, 200mg
- 1回1錠、1日2回内服
- 坐剤、1剤25, 50mg
- 1回1剤、1日1~2回挿肛
- 注射製剤、1A 50mg/5ml
- 1A+生食100ml、30分かけて
- パップ剤とテープ剤がある
- 1日1~2回貼付、1回あたりの枚数制限なし
パップ剤
- 白色、粘着性 弱、厚みあり
- 高齢者が使い慣れており、こちらを希望する人が多い
- また、皮膚が脆弱でも使いやすい
テープ剤
- 茶色、粘着性 強、薄い
- 伸縮性がよく、関節部に好都合
- テープ剤
- 経皮吸収率がものすごく良い
- 1日1回貼付、1回2枚まで
弱オピオイド
- 錠剤、1錠トラマドール 37.5mg, アセトアミノフェン 325mg
- 1回1錠、1日4回、4時間空ける
- 最大1回2錠、1日8錠まで
- 注射製剤、1A 15mg/1ml
- 1A+生食50ml、30分かけて
- 注射製剤、1A 0.2mg/1ml
- 1A+生食50ml、30分かけて
To be continued…
随時更新していきますのでお楽しみに。
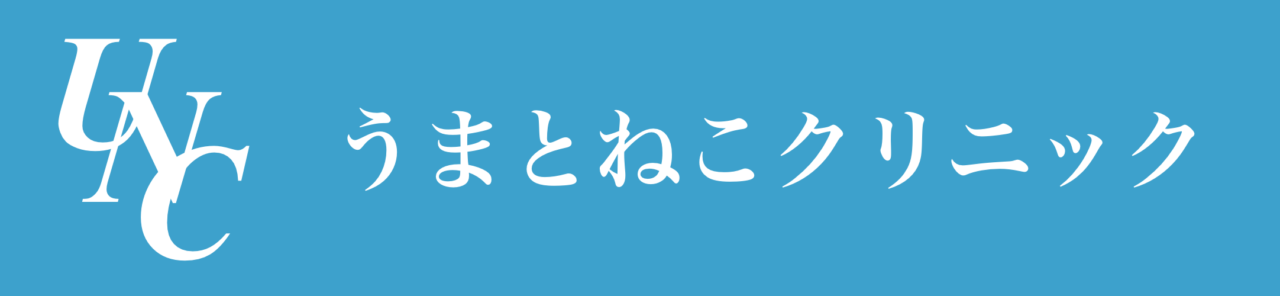

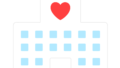

コメント