- 原因を探る
- レートコントロールに使える薬剤を知る
当直中、病棟看護師から、
「先生、心房細動でタキってます!」
というような相談を受けたとき、皆さんは自信をもって対応できますか?
今回は心房細動で夜中に呼ばれたときのアプローチの仕方と対応について、非内科系医師の方々に向けて、ざっくりまとめたいと思います。
あくまでざっくりです。考え方や最低限の知識を身につけましょう。
心房細動に遭遇したら
対応に迷うのは、
- 抗不整脈薬を使うべきか、否か?
- どの抗不整脈薬を選択すべきか?
の2点だと思います。
それぞれについてざっくり解説していきます。
無症状でバイタルサインが安定しており、心不全徴候などがない場合、基本的には抗不整脈薬は不要です。
むしろ、その患者さんの最大心拍数(220-年齢)を超えるような頻脈がある場合、
頻脈を引き起こす別の要因、例えば、
- 脱水
- 貧血
- 疼痛
- 発熱
などがないか検索する必要があります。
候補に挙がるのはβ遮断薬、ジギタリス製剤、Caブロッカーです。
いずれもレートコントロールを目的として投与します。
- ビソノテープ(ビソブロロール)→テープタイプ
- オノアクト(ランジオロール)→点滴製剤
使い勝手がいい反面、オノアクトは大変高価な薬剤。
病院的には病棟で気軽に使って欲しい薬ではないです…
- ジゴシン注(ジゴキシン)→即効性がある
長期投与で血中濃度管理が面倒。
- ワソラン(ベラパミル)
心機能低下に対して使いづらい。
結局どれ使ったらええねん‼という声が聞こえてきそうですが、
それぞれの注意点に気を付けてケースバイケースで使い分けるしかないというのが実際です。
うまとねこの初期研修病院では、ビソノテープとワソランがよく用いられていた印象でした。
禁忌さえなければ前述した薬剤を症例事にそれぞれ試しみて、
自分に合った一つなり二つを決めておくというのも手かもしれません。
- サンリズム(ピルシカイニド)
リズムコントロール、薬理学的除細動を目的として投与。
発作性心房細動に対して洞調律化を目指す治療戦略となります。
研修医の頃に、循環器内科の医師が頻脈性心房細動に対して、サンリズム(ピルシカイニド)を使っている場面を見たことがある人がいるかもしれません。
発作性心房細動で動悸を自覚している患者に対しては、有効な選択肢になり得ます。
ということで余裕のある方は頭の片隅に置いておきましょう~。
いろいろと説明が不足している点があると思いますが、この記事を足掛かりに学びが深まればうれしいです。
実際に薬剤を投与する際は十分に注意してくださいね。
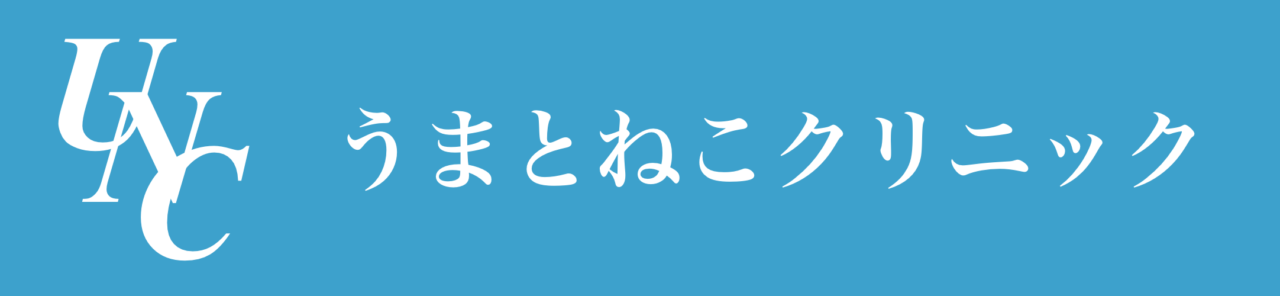


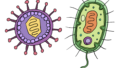
コメント